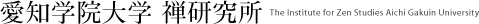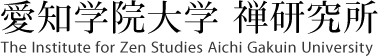禅書のしおり 令和6年度
竹村牧男著『良寛 その仏道』(青土社)

令和6年は、大愚良寛(1758-1831)の研究書が複数刊行されました。
中でも、特に良寛の思想に着目したのが本書です。第1部で良寛の伝記を挙げつつ仏道のあり方を検討し、第2部で良寛と浄土教・密教について示しました。
良寛の伝記には幾つか判明していない事柄が存在します。例えば、良寛は曹洞宗寺院で出家参学しましたが、正式な住職にはなりませんでした。本書では、良寛の師・大忍国仙の後に備中円通寺に入った玄透即中が提唱した、清規実践への見解の相違を理由に挙げています。また、良寛の漢詩である「詩永平録」の「永平録」は、道元禅師の『正法眼蔵』か『永平広録』かで議論されましたが、本書は『正法眼蔵』と推定し、良寛が残した『正法眼蔵』目録を分析しています。
本書は、良寛研究の現在を知ることができる一冊です。
川村悠人/アダム・アルバー・キャット著『パーニニ文法学講義』(臨川書店)
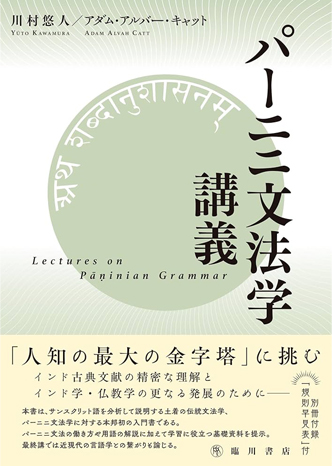
サンスクリット語(梵語)は、紀元前5世紀から4世紀に北西インドの地に登場した文法家パーニニが文法書『八課集』(アシュターディヤーイー)を著し、それによって標準化された言語です。インドの仏教徒も、やがてサンスクリット語を採用することとなりました。
『八課集』は「パーニニ文典」とも称され、その文法学は現代まで受け継がれています。サンスクリット語の文法書は既に複数存在するものの、パーニニの文法学そのものを解説する書籍は、本書が本邦初とされています。
本書第1講ではパーニニ文法学が俯瞰され、第2講では文法学の仕組みが詳細に解説され、第3講では学習のための諸資料が解説されています。
サンスクリット語は、仏教を学ぶ際にも重要であり、本書はその原点となるパーニニ文法学への格好の手引書です。