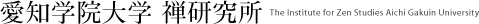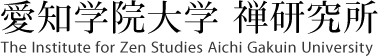禅語に親しむ 令和6年度
喫茶去(著・木村文輝)
先日、あるオークションで一本の掛け軸を入手した。カタログによれば、16世紀前半に京都大徳寺(だいとくじ)第76世となった古岳宗亘(こがくそうこう)の墨蹟とのことだが、その内容の解説がどうにも腑に落ちない。改めて掛け軸を眺めているうちに、思わず笑みがこぼれてきた。
師、垂示(すいじ)して(教えを説いて)曰(いわ)く「一椀の茶を喫して午睡から覚(さ)める時、どこに向けて機を転ずるか(心をどこに向ければよいだろうか)。」
ある僧云わく「必ず人は、水を飲んで冷暖(れいだん)を自ら知る(何事も、自ら体験してみなければわからない)。」
ある禅人云わく「一槌両当(いっついりょうとう)(物事にはいろいろな側面がある)。」
ある禅人云わく「万里一条鉄(ばんりいちじょうてつ)(全宇宙を一つの真理が貫いている)。」
ある僧云わく「常。」
師、代わりて曰く「趙州(じょうしゅう)和尚がここに在り。聴け。」
僧云わく「和尚、趙州和尚に代わり、一転語(いってんご)(悟りに導く言葉)を下されよ。」
師曰く「喫茶去(きっさこ)。」
この「喫茶去」という語は、引用中にも示されているように、中国唐代の趙州従諗(じょうしゅうじゅうしん)にまつわるもので、彼が新参の修行僧にいつも語りかけていたものである。当コラムでも既に初回(平成9年度)に神戸信寅先生が取り上げられているので、詳しくはそちらをご覧いただきたい。(『禅語にしたしむ』大法輪閣、禅研究所のホームページを参照。)
ここで紹介した掛け軸では、修行僧たちが、師の求めに応じてそれぞれに悟りの機縁となるような禅語を披歴したのに対して、師自身は、お茶を飲んでいる時には「お茶を飲みなさい」と語りかけている。お茶を飲みながら他のことを考えるのではなく、お茶を飲むことに集中しなさいということであろうか。
禅では、「而今(にこん)」、すなわち今、この瞬間に集中せよということが説かれる。あるいは、他の目的のために何かを行うのではなく、何事も、そのこと自体を目的として取り組むべきことが求められる。愛知学院大学の坐禅堂の前門にも掲げられているように、「喫茶喫飯一味禅(きっさきっぱんいちみぜん)」として、お茶を飲むことに集中することも、今を生ききる禅の極意なのである。
ただし、ここでの問題は、この師が「喫茶去」という語をどのような口調で語ったのかという点である。余分なことを考えずに、お茶を飲むことに専念せよという厳しい口調だったのか、それとも、まあ、お茶を飲みなさいという穏やかな口調だったのか。
道元禅師の説く「只管打坐(しかんたざ)」という語を、ひたすら坐れと理解するか、ただ坐れと解釈するかで先学の説明がわかれている。これに対して、坐禅とは、無意識に息を吸うように、「ジカに」坐ることだと説かれた故板橋興宗禅師の一文を拝見したことがある。息を吸う時に、その吸い方にとらわれていては、すぐに苦しくなってしまう。それと同じことで、肩に力をいれることなく、自然体で目の前のことに取り組む姿勢の大切さを述べられたのであろう。
そうだとすれば、お茶を飲む時には、肩ひじを張って気の利いた言葉を考えるより、まずはお茶を楽しみなさい。そんな感じで師は語りかけたのではないか。そう思いながらこの掛け軸を眺めていたら、何となくほっこりとして、思わず落札してしまった次第である。
(文学部教授)