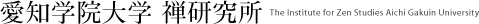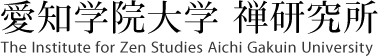研究会レポート 令和6年度
華厳から密教、そして禅へ ―8世紀における東アジア仏教思想の潮流―龍谷大学特任教授 吉田叡禮
東アジア仏教思想の中でも、今回は華厳と密教、禅という3つを採り上げます。中国華厳宗第4祖・清涼大師澄観(737-838)による弘法大師空海(774-835)への影響を示し、更に禅との連関性も考察します。
まず、密教の『大日経』に対する一行の註釈には華厳思想が多く含まれます。密教の基底では、華厳教学を参照して摂取しています。一方の澄観は、密教の不空三蔵の著作を参照し、『華厳経』「入法界品」に基づく不空の密教儀軌を全文引用し、華厳の観法としました。また、澄観は禅宗でも祖師に数える実践肌の人です。
空海『御請来目録』には、澄観の『華厳経疏』などが入り、自著でも引用されます。教学への影響としては、澄観の教判である十宗判と、空海が『秘密曼荼羅十住心論』で示した十住心を並べると、思想の優劣に関する順番が符合します。また、空海も主張した成仏論として、華厳と密教に共通する「現身成仏」「速疾成仏」などが説かれます。
一方で、澄観と時代が重なる馬祖道一(709-788)の「即心是仏」は、『華厳経』の教えに基づいています。そして禅宗では、経論上の議論を日常に落とし込む「機用」を重視しました。
つまり、8世紀の東アジア仏教思想史の傾向として、教理の追究から体験の重視という動きが見て取れるという問題を提起し、発表を終えたいと思います。