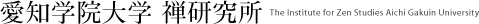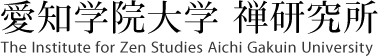研究会レポート 令和6年度
「批判仏教」をめぐって駒澤大学教授 奥野光賢
「批判仏教」とは、駒澤大学で教鞭を執られた袴谷憲昭先生によって1990年以降使用された用語で、定義は「仏教とは批判である」「批判だけが仏教である」とされます。
「批判仏教」の背景として、袴谷先生の「〈清浄法界〉考」(1976年)や、松本史朗先生の「『勝鬘経』の一乗思想について」(1983年)が挙げられます。更に、1979年に曹洞宗で発生した人権問題を検討する中で、1985年以降「業」の問題を扱う研究会に参加し、差別を構造的に生み出したとして、袴谷先生は「本覚思想批判」を、松本先生は「如来蔵思想批判」を展開します。
「批判仏教」に対する諸識者の見解として、高崎直道先生は1994年に、如来蔵思想がインド思想のヴェーターンダ=ウパニシャッド思想に近いというご自身の主張を共有しつつ、それが仏教では無いと即断することは躊躇しています。ただし、松本先生が如来蔵思想の構造的問題を示した「dhātu-vāda」仮説が唯識思想との共通する構造を示すものだと認めています。
批判仏教の曹洞宗への影響として、『正法眼蔵』の75巻本と12巻本との軽重を問う論点もあります。特に、初期の道元禅師の思想には如来蔵思想的な傾向が見られるとし、晩年の12巻本では払拭されたという見方も可能で、従来75巻本を重視していた曹洞宗学に課題として突き付けられました。また、松本先生は「仏性」論について、①仏性内在論、②仏性顕在論、③仏性修現(顕)論の3つに分類され、この内、①と③が修行必要論、②が修行不要論になると示し、道元禅師は③に相当するとしましたが、角田泰隆先生からの批判も存在します。
「批判仏教」ですが、重要なことは、文献研究客観主義への批判も伴っており、研究者も含め「仏教とは何か」を定めることを求めています。松本先生は「縁起」をもって仏教だとされ、そこから批判を展開します。方法論や思想の射程など、「批判仏教」が登場して40年を経る今でも、まだ多くの課題を突き付けているわけです。