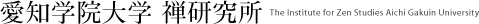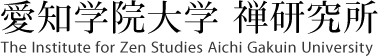禅滴 令和6年度
瑩山禅師の生涯(一)― 誕生をめぐって―(著・所長 河合泰弘)
昨年曹洞宗大本山總持寺では、開山瑩山紹瑾(けいざんじょうきん)禅師の700回大遠忌が盛大に勤修された。曹洞宗において瑩山禅師は、永平寺開山道元禅師(1200-53)とともに「両祖」と称され尊崇される禅匠であるが、道元禅師と比べて認知度が低いのが現状である。現在の曹洞宗寺院の殆どが、瑩山禅師の流れを引いていることから、瑩山派が曹洞宗発展の一翼を担ってきたことは間違いない。
瑩山禅師には、晩年の日記を中心に編纂された『洞谷記(とうこくき)』という資料がある。それによると、母親が37歳の時、夢に朝日の光を飲んで懐妊したこと、観音菩薩に身ごもった子が聖人ならば、安産であるように、そうでないならば、胎内で消し去ってくれと祈ったこと、毎日観音に三千三百三十三拝し、観音経を読誦すること7か月して産み落としたことを述べている。
出生に関する記事の中で、最も注目すべきことは、母親の祈った観音についてである。『洞谷記』「円通院之縁起」によれば、瑩山禅師が建立した永光寺の山内にある円通院の本尊は、禅師の母が、肌身はなさず「一生頂戴」し、随身した「十一面観音」であり、この観音像は、禅師の母が、18歳の時、その母と生き別れとなって、7、8年の間、行方が知れず、清水寺に願をかけて7日間日参したところ、その6日目に参詣の路上で十一面観音像の欠けた頭部をみいだし、これを拾いあげて、もし願いがかなって、わが母に会えることができたならば、欠けたるところを補って、一生頂戴之本尊としたいという祈念をしたところ、翌日、母のありかを確かめることができた。そこで、ただちに仏師に依頼して、十一面観音像を補修し、これを念持仏とし、懐妊後祈ったということである。
禅師の誕生地については、諸伝が、越前国多禰とするが、現在、福井県に多禰という地名はなく、次の2説が存在する。越前市帆山町説と坂井市丸岡町山崎三ヶ(やまさきさんが)説である。
このうち帆山説については、古くから認められていたようで、現にこの地に御誕生寺という一寺があり、また大本山總持寺もこの説を採り、昭和42年(1967)にこの地を誕生地と一応定めている。このこともあってか、總持寺をはじめ曹洞宗で出される禅師を紹介するものに、帆山町を誕生地としている場合が少なくない。
一方、丸岡町にも明治31年(1898)に建てられた「瑩山国師御誕生地」の碑がある。『永光寺中興雑記』(石川県永光寺蔵)に「多祢ハ越前丸岳(マルオカ)ノ脇キトイハラノ下多子(フモトタ)ノ村ラ也」と記しており、トイハラとは現在の丸岡町豊原と考えられ、山崎三ケに隣接していることから、これが書かれた1642年当時、永光寺では丸岡を誕生地とする伝承があったと推測される。
また、誕生年については、かつては文永5年(1268)という認識が主流であったが、現在では文永元年説が、諸氏の研究により定説化している。
(教養部教授)